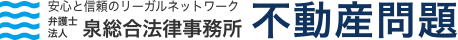不動産競売手続きにおける執行官の役割と現況調査について

不動産競売において、対象不動産の現況調査などの重要な役割を果たすのが「執行官」です。
執行官は、強制執行手続きを円滑に進めるため、民事執行法の規定に従って必要な職務を行います。
もしご自身の所有する不動産が競売の対象となり、執行官による現況調査に関する通知が届いた場合には、慌てず冷静に対応してください。
この記事では、不動産競売手続きにおける執行官の役割について、現況調査の点を中心に解説します。
1.不動産競売の大まかな流れと執行官の役割
まずは、不動産競売の大まかな流れを簡単に確認しておきましょう。
①不動産競売(強制執行)の申立て
確定判決などを債務名義(民事執行法22条)として、不動産の所在地を管轄する裁判所に強制執行を申し立てます(同法44条)。
②強制執行の開始決定・対象不動産の差押え
強制執行の申立てが適法と認められた場合、裁判所は強制執行の開始を決定し、対象不動産を差し押さえます(同法45条1項)。
差押え以降、債務者は対象不動産を処分することができなくなります。
③執行官による対象不動産の現況調査
執行官が、対象不動産の形状・占有関係・周辺状況などの現況調査(同法57条1項)を行い、競売価格を決定するための情報を収集します。
④評価人による対象不動産の評価
現況調査の報告書などを参照しながら、評価人(主に不動産鑑定士)が対象不動産の評価を行います(同法58条1項、2項)。
⑤裁判所による売却基準価額の決定
評価人の評価に基づき、裁判所が対象不動産の売却基準価額を決定します(同法60条1項)。
ここで決定された売却基準価額の80%相当額が、最低入札金額となります。
⑥入札
入札希望者が、入札期間中に1回限り、購入希望額を明記したうえで入札を行います(同法64条2項)。
なお、競り売り(期間中何度でも価格提示を行うことができる方式)は実務上行われていません。
⑦裁判所による売却許可決定
最高額の入札者につき、売却不許可事由(同法71条各号)が存在しないことが確認された場合、裁判所によって対象不動産の売却が許可されます。
⑧売却代金の納付・所有権移転
裁判所書記官が定める期限までに、買受人が代金を裁判所に納付すると、同時に対象不動産の所有権が買受人に移転します(同法78条1項、79条)。
⑨対象不動産の引渡し
対象不動産が、債務者または占有者から買受人に引き渡されます。
なお、債務者または対象不動産の占有者が引渡しを拒否する場合には、買受人の申立てによって裁判所が引渡命令を発し(同法83条1項)、その後引渡しの強制執行へと移行します(同法168条以下)。
⑨債権者への配当
競売代金が債権者へ配当されます(同法89条2項)。
これで不動産競売の手続きは完了です。
 [参考記事]
不動産競売の流れ
[参考記事]
不動産競売の流れ
上記の不動産競売手続きの流れの中で、「執行官」が果たす役割は以下の2つです。
<執行官の役割>
・対象不動産の現況調査を行う
・不動産の引渡しを拒否する債務者等に対して、引渡しの強制執行を行う
次の項目から、執行官の大きな役割である「現況調査」の詳細について解説します。
2.執行官による不動産競売の「現況調査」とは?
執行官による「現況調査」は、どのような目的で、またどのような流れで行われるのでしょうか。
実際に執行官が来るとなると身構えてしまう方が多いと思いますが、事前に現況調査の全体像を把握して、冷静に対応できるようにしておきましょう。
(1) 現況調査の目的
現況調査の目的は、競売の対象不動産について評価を行うことです。
不動産の価値は、立地や築年数などの客観的な情報だけでなく、形状・占有関係・周辺状況などの「状態の良し悪し」によっても変わります。
このような不動産の状態に関する情報は、現地で確認しなければ得ることができません。
そこで、執行官が実際に現地へ足を運び、対象不動産の状態を確認するのが「現況調査」の目的です。
執行官は、現況調査の後で報告書を作成し、裁判所に提出します。
その報告書の内容を踏まえて、裁判所に選任される評価人が、対象不動産の評価を行います。
(2) 現況調査は不動産鑑定士立会いの下、執行官が行う
現況調査には、執行官とともに不動産鑑定士が立ち会うのが一般的です。
不動産鑑定士は、物件の価値を左右する要素を熟知しているので、現況調査中、執行官に確認事項などを助言する役割を果たします。
そのため、実際の現況調査には、執行官と不動産鑑定士が2名でやってくることを想定しておきましょう。
(3) 現況調査の流れ・内容
現況調査が行われる場合、まず裁判所から現況調査に関する通知が届きます。
通知書の中には、現況調査が行われる日時が記載されていますので、その日時に立ち会うことができるかどうか、スケジュールを確認しましょう。
なお、スケジュールの都合が合わない場合には、裁判所と相談のうえで日程を変更してもらうことも可能です。
現況調査の当日には、前述の通り、基本的に執行官と不動産鑑定士が2名で対象不動産の現地を訪問します。
その後、執行官が不動産鑑定士の助言を受けながら現地を視察し、必要に応じて写真撮影などを行い、対象不動産の現況に関する情報を収集・記録します。
執行官による現地の確認が済んだら、現況調査は終了です。
その後、持ち帰った情報を基にして執行官が報告書を作成し、不動産評価のステップへと移行します。
3.執行官が現況調査に来る場合の債務者の対応
裁判所から現況調査に関する通知が届いた場合、どう対応して良いのかわからず慌ててしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし前述のとおり、現況調査はあくまでも現地の確認のみを目的としています。
すぐに不動産が取られてしまうわけではありませんので、慌てず冷静に以下のとおり対応してください。
(1) 現況調査の予定日時に必ず在室しておく
現況調査の予定日時に債務者(または占有者)が在室していない場合、執行官は鍵を強制的に開けて入室する権限を持っています(民事執行法57条3項)。
執行官に勝手に居室へ入られるのは気分が悪いでしょうし、中で執行官がどのような行動をとったかを確認する必要もありますので、現況調査の予定日時には必ず在室しておくようにしてください。
なお前述のとおり、通知された予定日時の都合が悪い場合には、裁判所に相談すれば日程を変更してもらうことも可能です。
もし日程の変更を希望する場合には、早めに裁判所へ連絡しましょう。
(2) 執行官に抵抗してはならない
執行官が現地を視察したり、写真を撮ったりすることを妨害すると、公務執行妨害罪(刑法95条1項)などの犯罪に該当するおそれがあります。
仮に抵抗したとしても、執行官には抵抗を排除するため、威力を用い、または警察上の援助を求める権限が与えられているので(民事執行法6条1項)、たちまち鎮圧されてしまうでしょう。
現況調査の段階では、執行官はあくまでも視察や写真撮影を行うだけであり、すぐに不動産が取られるわけではありません。
そのため、いったん現況調査の場では抵抗せず冷静に対応し、善後策を検討するのが良いでしょう。
4.現況調査後、任意売却を目指すのも有力
現況調査の後、債務者が何もしなければ、不動産の評価・入札を経て競売が実行されてしまいます。
競売の場合、売却価格が市場価格よりも低く抑えられるケースが多く、債務者の手残りが少なくなってしまう可能性が高いです。
これに対して、債務者が買受希望者と直接契約を結んで不動産を売却する「任意売却」であれば、競売よりも高い価格での売却を実現できる可能性があります。
任意売却には債権者の承諾が必要であり、かつ買受希望者を見つけてくる必要があります。
この点、弁護士にご相談いただければ、適宜不動産業者と連携のうえで、法律上・取引上の両観点から依頼者をサポートいたします。
不動産競売を避け、より有利な条件で任意売却をしたい場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
 [参考記事]
競売申立された不動産を任意売却できるのはいつまで?
[参考記事]
競売申立された不動産を任意売却できるのはいつまで?
5.まとめ
不動産競売の開始が決定されると、執行官による現況調査が行われます。
現況調査はあくまでも現地の視察・写真撮影などによる状況把握が目的であり、すぐに不動産が奪われてしまうわけではありません。
そのため、現況調査の当日は冷静に対応したうえで、その後任意売却などの善後策を模索しましょう。
不動産競売手続きへの対応にお悩みの方、競売を避けて任意売却をしたいとお考えの方は、一度弁護士までご相談ください。